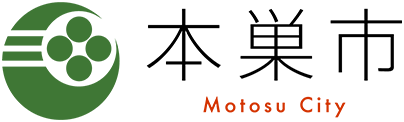本巣市手話言語条例が制定されました
- [更新日:]
- ID:2811
本巣市手話言語条例は、手話が音声言語と同等の言語であるとの認識に基づいて、手話への理解を広げることにより、安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、手話言語に関する基本理念や各主体の役割などを定めたものです。令和7年第2回本巣市議会定例会において可決し、制定されました。

条例の施行に伴う施策
条例に定めた施策を推進するために、具体的な取組みを実施していきます。
令和7年度については、市が主催する式典やイベント等において手話通訳者を派遣し、市民が手話言語による情報を得る機会の拡大と手話言語に対する理解の促進を図ります。
また、市の職員に対して手話についての研修会を実施し、手話言語への理解を深めます。
さらに、意思疎通支援者の養成や手話言語による意思疎通が容易になることを目的として、今後も引き続き、手話奉仕員養成研修事業や意思疎通支援事業を実施します。
| NO. | 式典等の名称 | 開催予定時期 |
|---|---|---|
| 1 | 令和7年度淡墨桜感謝祭 | 4月4日 |
| 2 | 東海環状自動車道本巣IC・本巣PAの開通記念イベント事業 | 11月ごろ |
| 3 | 20歳を祝う会 | 1月11日 |
| 4 | 中学校卒業式 | 3月上旬 |
| 5 | 小学校卒業式 | 3月下旬 |
| 6 | 幼児園卒園式 | 3月下旬 |
条例の概要
前文において、手話が視覚的に表現される一つの言語であることを述べ、この条例を制定するに当たっての背景や、手話に対する理解を広げることにより安心して暮らすことができる地域社会を実現することを説明しています。
目的
手話が言語であることの理解の促進や、手話言語を使用しやすい環境の整備に関して基本理念を定め、市の責務と市民等の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、地域共生社会を実現することを目的としています。
基本理念
- 手話言語に対する理解の促進は、手話が言語であるという認識に基づき手話言語に対する理解を広げ、ろう者とろう者以外の人がお互いに人格および個性を尊重し合う地域共生社会を目指して行います。
- ろう者が手話言語による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されることを基本として行います。
市の責務
市は、基本理念にのっとり、手話言語への理解の促進を図り、ろう者があらゆる場面で手話言語による意思疎通ができ、自立した日常生活や地域における社会参加がしやすい環境を推進するための施策を実施します。
市民等の役割
- 市民は、ろう者のコミュニケーションにおける手話の必要性について理解し、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めます。
- ろう者は、手話言語の意義および基本理念に対する理解の促進と手話言語の普及に努めます。
- 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めます。
施策の策定および推進
- 手話言語に対する理解と手話言語の普及を図るための施策
- 市民が手話言語による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策
- 市民が手話言語を使用しやすい環境の構築のための施策
- 手話通訳者等の確保と養成に関する施策
- そのほか、市長が必要と認める事項
市は、以上の施策を推進します。
条例の施行日
令和7年3月24日
手話動画
以下をクリックすると、条例の内容を手話で説明した動画をご覧いただけます。(市公式YouTubeチャンネルにリンクします)
ダウンロード
本巣市手話言語条例
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます