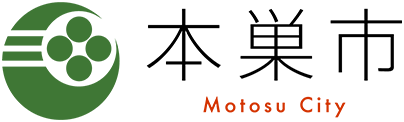令和7年 第2回市議会 所信表明 令和7年2月20日
- [更新日:]
- ID:2763
令和7年第2回本巣市議会定例会の開会にあたり、新年度予算をはじめ、提出議案のご審議をお願い申し上げるに先立ちまして、新年度における施策の大綱と私の市政運営に関する所信を申し述べさせていただき、議員各位並びに市民の皆様のなお一層のご理解とご協力をお願い申し上げたいと存じます。
市政運営方針
まず、はじめに、市政の推進にあたり、私が基本とする市政運営につきまして申し上げます。私は、市長として、市政をお預かりして以来、市政の推進にあたり、市民の皆様の声をよく聞く、「現場主義」「対話主義」「市民目線」を基本姿勢に、市政運営に努めてまいりました。
新年度におきましても、引き続き、こうした市政運営を基本姿勢に、私が重点的に取り組んでいくとしております6つの基本政策に基づき、5年後、10年後も「ますます元気で笑顔あふれる本巣市」であり続けられるよう、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
予算編成方針
それでは、国の令和7年度予算編成および令和7年度地方財政対策に基づき編成いたしました新年度予算の概要につきまして、ご説明申し上げます。
まず、国の令和7年度地方財政対策によりますと、普通交付税の交付団体ベースによる「一般財源総額」は、社会保障関係費、人件費の増加や物価高が見込まれる中、地方団体が、さまざまな行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、前年度比1.7%、1兆535億円増の63兆7,714億円が確保され、前年度を上回る額となったところでございます。
また、地方公共団体の重要な財源であります「地方交付税」につきましても、前年度比1.6%にあたる2,904億円増の18兆9,574億円となっており、かつ、交付税の振り替え財源である臨時財政対策債は、制度創設以来初めての新規発行額が計上されないことに加え、交付税特別会計借入金の償還繰延べ分2兆2,000億円の償還が計上され、地方財政の健全化が大きく図られている状況でございます。
地方財政は、人口減少や少子高齢化が深刻化する中で、社会保障関係費の増加はもとより、物価高騰による自治体のサービス・施設管理などの経費の増加に加え、多発する災害に備えるための防災・減災対策に要する経費や子ども・子育て政策の強化、デジタル化・脱炭素化などの財政需要が見込まれ、更には、仮に今後、いわゆる「103万円の壁」に係る基礎控除額等の引き上げの見直しが行われれば、地方財政に大きく影響するものと思われます。
次に、本市の財政状況を申し上げますと、合併以来、財政の健全化を維持していくため、行財政改革大綱に基づく「行財政改革実施計画」の着実な推進、さらに、毎年の予算編成にあたり、経常経費を一定額削減する取り組みや有利な地方債の活用、安定した市税収入の確保などに努めてまいりました。その結果、財政の健全化判断比率は、国が示す基準以下となっており、現段階では、健全性は保たれている状況でございます。
しかしながら、今後の財政見通しでは、歳入につきましては、我が国を取り巻く社会経済の不透明な状況が依然として続く中、長引く物価高騰により生産コストが上昇し、食料品など市民生活に身近な商品が高騰しており、消費者物価は上昇するものの、物価上昇を上回る賃上げの定着がなければ個人消費が足踏みすることが予測され、経済に与える影響が懸念される中で安定した自主財源の確保は厳しい状況が見込まれます。
一方、歳出は、少子高齢化社会の進展により、医療や介護などに要する経費、いわゆる社会保障関係費の増加が続いており、賃上げに伴う人件費や適正な価格転嫁による労務費の増加、さらには、エネルギー価格の高騰による光熱費なども年々増加しております。加えて、建物、道路、橋りょうなどの長寿命化、公共施設の統廃合に係る経費も見込んでいく必要があります。また、金利上昇に伴う地方債の借入利率の上昇や、東海環状自動車道の周辺道路や新庁舎の整備などに活用してきた合併特例債などの公債費は増加傾向にあり、後年度の償還額について交付税措置があるものの、厳しい財政運営が見込まれます。
このため、将来にわたって財政の健全性を保ちつつ、持続可能な自治体、元気で笑顔あふれるまちを実現していくためには、これまでの改革の手を緩めることなく、本巣市にとって何が最適かを常に考え、前例踏襲にとらわられることなく、限られた財源の中でより高い成果を目指して「選択」と「集中」を繰り返し、新たな「施策の推進」と「財政の健全性」の両立を図ってまいりたいと考えております。
こうした本市の財政状況を踏まえながら、編成いたしました令和7年度一般会計当初予算につきまして、まず、歳入でございますが、自主財源の柱である市税収入は、個人所得の回復や景気の緩やかな回復による企業収益の増加が見込まれ、また、令和6年度分の個人住民税の定額減税終了に伴い大幅な増額を見込んでおります。固定資産税も市内企業の新工場の完成により増額となっております。市税全体では、対前年度当初比、約2億8千万円増の55億2千万円余を見込んでおります。
地方交付税につきましては、主に財源不足額に対する臨時財政対策債の発行額の皆減に伴い普通交付税が増額となり、対前年度当初比、2億5千万円増の50億2千万円を見込んでおります。
地方譲与税、地方消費税交付金など国からの交付金は、定額減税の終了に伴い地方特例交付金が減額となり、対前年度当初比、約6千5百万円減の13億6千万円余を見込んでおります。
国庫支出金につきましては、児童手当の抜本的拡充に伴う制度改正などにより国庫負担金が約2億2千万円増加し、全体で17億3千万円余を見込んでおります。
寄附金につきましては、ふるさともとす応援寄附金で返礼品の新規開拓やポータルサイトのブラッシュアップなどの取組により過去最高の寄附額を更新したことから、前年度とほぼ同額の10億円余を見込んでおります。
繰入金につきましては、主に庁舎整備事業の完了などにより公共施設等整備基金からの繰入金が皆減したことで、対前年度当初比、約8億4千万円減の7億5千万円余を見込んでおります。
また、市債につきましては、本巣消防署整備事業等に伴う緊急防災・減災事業債、市道西部連絡道路線道路舗装事業等に伴う緊急自然災害防止対策事業債の増加などにより、対前年度当初比、約6億円増の21億5千万円余を見込んでおります。
歳出におきましては、新年度も「元気で笑顔あふれる本巣市づくり」を目指し、市民の安全・安心を守るための消防署整備事業や、児童生徒がDX時代を生き抜いていける環境を整えるICT機器整備事業をはじめ、引き続き「教育・子育て支援」「移住・定住対策」「景気・雇用対策」「防災対策」などの事業にもきめ細かく関連経費を盛り込んでおります。
また、東海環状自動車道「本巣IC」の開通を4月に控え、加えて、夏頃には本巣PAもオープンの予定であり、今後、本巣市の交流人口は大幅に増加することが見込まれます。そのため、この機会を逃すことなく、チャンスと捉え、人の流れを生み出し、滞留させることで地域経済の好循環を拡大させていきます。その手始めとして、新年度は開通記念イベントとして、市民や企業、行政のそれぞれが主役となり、それぞれの特性を生かしたイベントを作り上げていきます。地域の魅力を最大限に引き出し、市民や観光客に楽しんでもらえる、魅力的なイベントを実施してまいります。
さらに、今年度、市が実施する全ての事業を対象に、一切の聖域を設けずゼロベースから事業効果や手法などを精査し、「市民ニーズに適しているか」、「前例踏襲で漠然と続けていないか」など、外部評価委員をまじえて、あらゆる面から厳しく事務事業の総点検を行いました。新年度予算では、外部評価の意見を踏まえ、事業継続の可否や手法の検討などしっかりとPDCAサイクルを回しながら、市民目線での「選択」と「集中」に努め、市民に寄り添った施策の展開ができるよう、ソフト事業を中心に新たな事業や拡充強化のための予算を計上し、よりきめ細やかな予算編成に努めたところであります。
こうした歳入歳出の見込みにより編成いたしました新年度の一般会計当初予算の総額は、対前年度当初比で2.7%、5億3千万円増の202億5千万円となっております。
当初予算が増額となった主な要因は、「消防署整備事業」および「本巣北分署整備事業」が約5億4千万円、「道路緊急自然災害防止対策事業」が約3億5千万円、「学校ICT機器整備事業」が約2億5千万円の増額となったことが大きく影響しており、「庁舎整備事業」が約10億円の減額となっていますが人件費の増額もあることから、予算総額は昨年度を上回り、過去3番目に大きい予算規模となっております。
特別会計につきましては、「国民健康保険特別会計(事業勘定)」では、国民健康保険の被保険者数の減少に伴う療養給付費の減額による減、「国民健康保険特別会計(施設勘定)」では、医師等の退職による人件費の減額などにより減となっております。
「後期高齢者医療特別会計」では、後期高齢者医療広域連合納付金の増額などにより増となり、「企業用地造成事業特別会計」では浅木地区企業用地造成事業における造成工事費の減額による減となっております。
新年度の特別会計予算の総額は、対前年度当初比で2.5%、1億1千5百万円減の44億5千1百万円でございます。
「水道事業会計」につきましては、主に営業設備費の減少により、予算の総額は、対前年度当初比で1.1%、約1千7百万円減の16億3千万円余となっております。
また、「下水道事業会計」につきましては、主に処理場建設改良費の増額により、予算の総額は、対前年度当初比で1.7%、約3千万円増の17億7千万円余となっております。
基本政策への取り組み
それでは、令和7年度予算の主な施策につきまして、ますます「元気で笑顔あふれる本巣市づくり」を目指し、重点的に取り組む6つの基本政策に基づき、順次ご説明を申し上げます。
元気な里づくり
活力
まず、基本政策の一つ目は、将来にわたって活力のある地域にするため、企業誘致をはじめ、商工会などと連携した活力のある商工業の振興、観光振興や魅力ある特産品の開発など新たな産業の生まれる「まちづくり」を推進してまいります。
活力あふれる元気な本巣市を築くためには、産業の創出や雇用の場の確保が欠かせません。東海環状自動車道の山県ICから本巣ICまでの開通が4月6日と発表され、また、本巣ICから大野神戸ICの区間も今年の夏頃に開通予定となっております。両区間の開通により、アクセス性が格段に向上し、地域間の往来がより便利になることで、広域集客の促進や輸送時間の短縮などが期待されており、本巣市のポテンシャルは一層高まってまいります。この高いポテンシャルを最大限活用できるよう、市内への企業誘致と雇用創出を推進してまいります。新年度におきましては、浅木地区に加え、北屋井地区でもオーダーメイド型の企業用地造成事業を進めることとしており、引き続き新たな企業の誘致に向け、取り組んでまいります。
さらに、これまで東海環状自動車道の開通を見越し、もとまるパークや都市計画道路の長良糸貫線など、地域の活気、賑わいの創出に向けた整備を進めてまいりましたが、今後、それらの相乗効果をより一層、飛躍させていくためにも、「都市計画マスタープラン」の改定にあわせ、「立地適正化計画」を策定し、住宅や医療・福祉施設、商業施設などさまざまな都市機能の持続性を高めていくことで、将来にわたって活力のある地域づくりを進めてまいります。
景気・雇用対策につきましては、主要な幹線道路の整備、地域内の生活道路や防災・交通安全対策などの普通建設事業費に所要の予算を配分し、景気対策に努めるとともに、市内の事業者への優先発注などを通じ、地域経済へ寄与できる予算を確保してまいります。
また、引き続き工業団地へ誘致した企業に対し、市民の雇用を働きかけ、市民を常用従業員として雇用した場合には「雇用奨励金」を交付することで、市民の雇用の場を確保してまいります。
さらに、商工会と連携し、急激な円安などによる物価高騰や環境問題、いつ起こるかわからない災害時への対応など、目まぐるしい社会変化の中でも努力を惜しまない市内事業者の事業活動継続と活性化を目的に「事業者サポート補助金交付事業」などを通じ、市内事業者への支援を、引き続き行ってまいります。
加えて、地域公共交通事業者であります樽見鉄道に対しても、「もとまる商品券」と企画列車等をセットにした事業に補助することで、誘客拡大による鉄道事業の経営安定化と地域における消費喚起を促し、継続的な市内消費の増大による地域活性化を図ってまいります。
農業対策につきましては、かけがえのない農地の保全のため、土地改良事業による圃場整備を進め、担い手の確保に努めてまいります。また、新規就農者に対してもきめ細やかな支援を進め、地域農業への定着を図るとともに、ロボット技術やAIを活用したスマート農業技術の導入を支援し、作業の省力化・効率化につなげることで、担い手不足や労働力不足の解消を図るなど、引き続き、農業経営の安定化に向けた取組を進めてまいります。
林業振興につきましては、森林経営管理制度を活用した林業経営の効率化と森林管理の適正化を促進し、森林の環境保全や防災機能の向上など多様で健全な森林への再生に取り組みます。また、森林技術者の担い手対策は重要な課題であり、資材運搬ドローン等のICT技術導入を支援することで、労働生産性を向上させるとともに、危険が伴う作業の軽減を図り、林業労働の魅力向上にもつなげてまいります。
ふるさと納税制度を活用した地場産品の開発につきましては、昨年9月に条例を制定し、市の地域特性を生かした魅力ある地場産品の創出に向けた取組を進めてまいります。クラウドファンディングを活用し、市と市内事業者の共同で立ち上げたプロジェクトに賛同いただいた方の寄附を原資に、サービス提供に向けた施設整備に支援をしてまいります。ふるさと納税は、市内事業者の販売促進や市のPRにもつながることから、改めて市内事業者等と連携し、魅力的な地場産品の充実に積極的に取り組んでまいります。
温もりのある里づくり
安心
次に、基本政策の二つ目は、少子化対策や子育て支援などにより、安心して地域でこどもを育てることができる「まちづくり」を推進してまいります。
こどもは「地域の宝」、これからの本巣市を担っていく私たちの未来です。こどもが個人として尊重され、地域全体でこどもや子育て家庭への理解を深め、安心してこどもを産み育てることのできる環境を実現するためには、こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、支援していくことが必要です。
令和7年度からは、「こども基本法」の基本理念や「こども大綱」の基本的な方針を踏襲しつつ、これまでの「子ども子育て支援事業計画」を包含(ほうがん)した「本巣市こども計画」がスタートします。
すべてのこどもや若者が心豊かに育ち、保護者が喜びや生きがいを感じながら子育てができ、すべての人がこどもと一緒に元気になれるまち「本巣市こどもまんなか社会」の実現を目指してまいります。
まず、一つ目はライフステージを通した施策の推進です。
こどもたちが多様な遊びや体験ができるよう、留守家庭教室や延長保育、預かり保育など、家庭の事情により行動に制限を受けるこどもが集まれる場所を引き続き確保してまいります。
また、こどもの貧困対策として、貧困の解消・連鎖を断ち切るために、「本巣市奨学金返還支援制度」の普及を推進し、奨学金の返還に負担を感じている若年層を経済的に支援するとともに、市内への定住促進や市内での労働力確保につなげてまいります。
さらに、児童虐待防止の支援として、子育て世帯訪問支援事業に新たに取り組みます。家事や育児に不安や負担を抱えた子育て家庭を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みに耳を傾けながら家事や育児に対する支援を行うことで、家庭や養育環境を整え、虐待リスクの高まりなどを未然に防ぐよう努めてまいります。
次に、二つ目はライフステージ別の施策の推進です。
こどもの誕生前から幼児期までは、人生の確かなスタートを切るための最も重要な時期です。令和7年度からは、国の「成育医療等基本方針」を踏襲して作成した「本巣市母子保健計画(第三次)」に基づき、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して、保健師等が妊婦や子育て家庭に寄り添い、身近に相談に応じることで、その後の必要な支援につないでいく「伴走型相談支援」の充実を図ってまいります。その他にも、ファミリー・サポート・センターや子育て支援センター、子どもセンターなどを通じて、子育て家庭の育児相談や支援、地域の人とのつながりを作り、育児への不安の解消を図ってまいります。
また、新年度は新たな取組として、生後6か月から満3歳未満の保育所等に通っていない子どもの育ちを支える「こども誰でも通園制度」を開始いたします。国においては、令和8年度から全自治体での実施としていますが、それに先駆け実施するものです。家庭とは異なる経験や子ども同士のふれあいを通して、子どもの健やかな成長を支援するとともに、子育てに悩みや不安を抱えている保護者に寄り添った支援を進めてまいります。市内幼児園と小規模保育施設において就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用ができ、多様化する保育ニーズへ官と民が連携して対応することで、市内の子育て環境を充実させてまいります。
さらに、学童期や思春期などそれぞれのステージに応じた施策を展開してまいります。
学童期や思春期は、身体も心も大きく成長する時期であり、小さな失敗を経験しながら成功体験を重ね、自己肯定感を高めることができる環境を整えていく必要があります。伝統文化や芸術活動など地域や学校の特色を活かした生きる力を育てる教育活動の推進や学習状況に即したきめ細かい少人数指導の充実を図ってまいります。また、健康や性に関する正しい知識の習得にも、関係機関や家庭と連携して取り組んでまいります。
次に、三つ目は子育て当事者への支援です。
本市では、これまでも全てのこども、子育て世帯に対して、親の働き方やライフスタイル、こどもの年齢に応じて、切れ目のない経済的な負担軽減や支援に努めてまいりましたが、引き続き、子育て世帯へのさまざまな手厚い支援を行ってまいります。
子育てや教育に関する経済的負担の軽減としましては、出産祝金の支給や保育園の保育料軽減、18歳まで拡充した医療費の無償化、小学校新1年生にはランドセルとヘルメットの入学祝い品の贈呈、多子世帯の援助として給食費の助成など、それぞれの段階で切れ目のない負担軽減策を着実に実施してまいります。また、夫婦が協力しながら子育てし、それを職場が応援できる、共働きや共育てを地域全体で支援する取組も推進するとともに、ひとり親家庭が抱えるさまざまな課題に対して、親子それぞれの状況に応じた細やかな支援が適切に行われるよう取り組んでまいります。
そうした中でも、市として特に力を入れているのが学校給食です。他の学校に負けない質の高い美味しい学校給食は、子どもたちが待ち望んで楽しみにしています。手作り感あふれる家庭の味を求め、栄養教諭や給食アドバイザー、調理員が常に努力しているからこそ、実現できています。給食は生きた教材です。健康な身体の基盤づくりはもちろん、食事のマナーや食べ物への感謝、家庭での給食の話題などを通して、食への関心を高めています。物価高騰により米の価格が過去に例を見ない高騰となっておりますが、使用食材の品質を落とさないよう、しっかりと支援していくとともに、本巣市産の野菜やジビエなどの食材を使用し、「ふるさと食材の日」や「もとまる給食の日」「児童生徒が考えた料理」などの取組をこれからも継続し、学校給食の充実と市内生産者の育成につながる事業として推進してまいります。
こうした取組を包括的に展開することで、安心して地域でこどもを育てられるまちを実現してまいります。
福祉
次に、基本政策の三つ目は、地域で支えあい、高齢者や障がいのある方々が、安心して健やかにいきいきと暮らせる「まちづくり」を推進してまいります。
高齢者対策につきましては、新年度から新たな取組として「高齢者向けeスポーツ教室」を開始します。eスポーツの魅力は、誰でも簡単に楽しく取り組め、世代同士や異世代との交流が図られることです。高齢者が家庭用ゲーム機などによるeスポーツを通じてフレイル予防や認知症予防に取り組み、一人でも多くの方が長く、健康で生活できるよう支援いたします。
その他にも、「脳を元気にする教室」や「体を元気にする教室」、「もとまるトレーニングクラブ」など、高齢者の方に関心をもってもらえるよう、さまざまな介護予防教室を用意・工夫してまいります。
また、フレイル予防で重要とされる「社会活動への参加」につきましても、高齢者タクシー利用助成事業などを通じて外出の機会をつくり、自宅などでは味わえない時間を過ごし、さまざまな刺激を得られる社会参加への機会提供にも努めてまいります。
障がい者対策につきましては、障がいのある人が地域で安心して暮らすことができる社会を目指し、手話が言語であることを明確にする「手話言語条例」の制定を進め、手話の普及啓発に努めてまいります。
また、新庁舎開庁に合わせ設置いたしました「福祉総合相談室」では、子育て家庭や高齢者、障がいのある方など相談者からの福祉に関する困りごとをワンストップでお受けしており、複雑化・複合化する生活課題に寄り添いながら、関係する機関と連携を密に調整しながら、家庭全体の支援につなげてまいります。
安全
次に、基本政策の四つ目は、豊かな自然環境を保全し、防災対策や交通安全対策などにより、心豊かに暮らせる「まちづくり」を推進してまいります。
まず、防災対策についてです。
令和6年1月1日に発生いたしました「能登半島地震」では、家屋の倒壊、大規模火災、津波により甚大な被害が発生し、今もなお、被災した地域での生活再建が厳しい状況が続いております。1日も早い復旧・復興、そして被災された方に平穏な日々が戻りますよう、心より願っております。
地震を含む自然災害はいつ、どこで発生するかわかりません。8月には日向灘を震源とする地震が発生し、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表され、その後、南海トラフ地震の30年以内に起こる確率が「70から80%」を「80%程度」に引き上げられております。
また、県内でも8月には台風10号により西濃地方を中心に大雨に見舞われ、大垣市、池田町、養老町で浸水被害が発生しております。
こうした災害に対して、あらゆるリスクを見据えて、いかなる自然災害が発生しようとも、人命の保護、重要機能の維持、被害の最小化、迅速な復旧復興が行えるよう「国土強靱化地域計画」を更新いたします。これまでの災害での教訓や、職員の災害派遣で得たノウハウをしっかりと取り入れながら、災害に強く、しなやかな本巣市を作り上げてまいります。
また、災害発生時はもとより、市民の生命、身体、財産を常に守っていくために、消防広域化に伴う適正配置計画に基づき、「本巣消防署」および「本巣北分署」の整備も進めてまいります。
その他にも、災害に備え、防災士の養成や自治会の「地区防災計画」の策定支援を進めるほか、災害時に協力いただける井戸所有者を増やすための普及啓発や、市役所本庁舎にも災害発生後の停電時でも使用できる手動式の井戸揚水設備を整備してまいります。
また、避難所の暑さ対策など避難生活の環境整備のため、残りの2校となっておりました土貴野小学校と根尾学園の体育館に空調設備を設置することで、市内小中義学校すべての指定避難所の環境整備が整うこととなります。
防犯対策につきましては、登下校時の見守り隊や防犯灯の設置を進めるとともに、もとメールを活用した防犯情報の発信など警察や学校、関係機関との連携を密にした取組を進め、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進してまいります。
交通安全対策につきましては、交通安全大会や交通安全教室などを通し、こどもから高齢者まで交通事故のない安全・安心なまちへ向けた普及啓発活動を行うとともに、学校、PTAや自治会などからの要望を踏まえ、新年度も引き続き通学路に交通安全対策を実施してまいります。
うるおいのある快適な里づくり
快適
次に、基本政策の五つ目は、幹線道路網や都市公園の整備、また公共交通機関のネットワーク化などにより利便性を高め、住みやすく快適な「まちづくり」を推進してまいります。
まず、道路整備につきましては、先程も申し上げましたとおり、東海環状自動車道の山県ICから本巣ICまでが4月6日に開通し、本巣ICから大野神戸ICの区間も今年の夏頃に開通予定となっております。開通を機にアクセス性が格段に向上することから、商業施設への広域集客や輸送時間短縮による工場立地などが期待されており、本市への経済効果は計り知れないものがあります。そうした経済効果を逃さないためにも、企業立地に伴い必要となる幹線道路やアクセス道路など、本市の景気対策にも資する道路整備を県など関係機関とも協力しながら、引き続き進めてまいります。
一方で、開通により市内の交通量も増加することが想定されることから、集落間を繋ぐ道路や通学路など市民生活に密着した道路には、歩行者・自転車空間を確保するなど、快適であるとともに安全・安心な道路整備を進めてまいります。
次に、都市公園「もとまるパーク」につきましては、施設の一部開園以降、市民の憩いの場として非常に多くのこどもたち、家族連れの方々に楽しんでいただいております。さらに、本巣PAの供用が開始し、公園と連結すれば、更なる公園利用、地域振興につながるものと期待をしております。このチャンスをつかむためにも、「もとまるパーク」の指定管理者と連携を密に、民間事業者のノウハウをしっかりと発揮していただき、きめ細やかな質の高いサービスを提供することで、集客効果を地域へ波及させていきたいと考えております。
そのため、新年度は「もとまるパーク」周辺に新たな賑わい、魅力を創り出すための、PFI手法を主体とした民間活力導入の可能性調査を進めてまいりたいと考えております。「もとまるパーク」との差別化を図り、子育て世代を中心に賑わいがあふれる場所を目指して、周辺エリアに新たな活気を吹き込んでいきたいと考えております。
公共交通につきましては、高齢化や人口減少、東海環状自動車道などの道路網の整備が進む中で、市民がより暮らしやすいまちにしていくため、新たな「地域公共交通計画」を策定いたします。既存の公共交通や将来を見越したデマンド交通、ライドシェアなどの導入も視野に、市民生活に欠くことができない地域の公共交通機関を確保・維持し、市民の利便性の向上を図ってまいります。
また、市営バスの故障時など多目的に利用が可能な、マルチパーパスモビリティ「マルモビ」を新たに導入します。「マルモビ」には電動ステップがついており、高齢者や障がい者の乗降を安全かつスムーズに行えるため、緊急時の代替車両として活用できるほか、災害時にはトイレや救護所、荷物輸送車など1台の車両を多方面、多目的に活用できます。こうした平時でも有事でもマルチに活用できる車両を公用車として配備してまいります。
環境対策につきましては、脱炭素社会の実現に向けて2月5日にゼロカーボンシティを宣言しました。市では既に、市民や事業者とともに「リデュース」「リユース」「リサイクル」の3Rの取組をはじめ、ごみの減量化、太陽光発電設備の導入など脱炭素社会に向けた取組を進めております。また、市役所新庁舎ではZEB(ゼブ)庁舎として市民サービスや執務環境の快適性を確保しながら、エネルギーを削減する環境負荷に寄与した庁舎となっております。
本巣市は森林が8割以上を占め、清流根尾川や豊かな自然、多くの文化財とともに暮らし、文化を育んできました。この市が誇る宝を、次世代に継承していくためにも、市民、事業者とともに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指して連携、協力を図りながら、取組の支援と普及促進に向けた啓発活動を進めてまいります。
育成
次に、基本政策の六つ目は、次代を担う子どもたちの教育環境づくりや、市民と行政が協働する市民の自発的な活動の支援、生涯にわたり学べる環境づくりを進めることで、元気な「まちづくり」を推進してまいります。
本巣市では、すべての人々が学ぶ当事者、生きる主体者となって自らが求める姿を目指すことを教育のコンセプトにしています。
そうした中において、子どもたち自身が生きる主体者となって「こどもまんなか社会」の実現を目指して、「本巣市こども権利条例」の制定を進めてきました。小中義学校の児童生徒、2,514人が「とびっきりの自分の一条」を考え、だれにとっても幸せになれる条例をつくるために、幾度となく話し合い、時には意見をぶつけ合いながら、自分たちの手で条例を創っていこうと強い決意のもと、考えてきました。監修者である木村泰子先生のお力もお借りしながら、話合いでの気付きや矛盾を繰り返し、子どもたちの口から「一人一人」「みんな」など、具体的な仲間の姿が浮かび、その仲間の幸せを願う、そのような気持ちのこもった、誰もが幸せになる権利条例となっております。
今回の「こども権利条例」制定の過程の中で子どもたちは、対話を通して学び、粘り強く立ち向かいながら自分たちで自己決定していくことで、自分の手で未来を切り開く、そんな力をつかむことが出来たのではないかと考えております。今後も、子どもが主体者となって自らの幸せな人生を切り拓く力を育成していくために、学びやすい環境と学び続けられる教育の充実に努めてまいります。
その一つとして、新年度は小中義学校のICT機器の整備を進めます。児童生徒、教職員のタブレット端末を更新するとともに、大型液晶ディスプレイの配備やデジタル教科書、プログラミング学習用キットなども導入します。小中義学校のICT環境をさらに充実させ、その利活用を促進させることで、授業の質を高め、児童生徒の情報活用能力の育成や自発的な学び、創造性を発揮できるような教育環境を整えてまいります。
また、確かで豊かな学びを実現させるため、根尾学園で実践している「かがやき科」や「ふるさと科」の成果を市内の小中学校に還元し、市内の探究学習の充実を図ってまいります。
さらに、増え続ける不登校児童生徒に対して適切な支援が行えるよう、引き続き、教育センター所長や子ども支援対策監を中心とした相談・支援体制の充実を図るとともに、適応指導教室のたんぽぽ・学び舎をはじめ、不登校関係の民間施設、NPOとの連携を適切に図り、地域ぐるみのサポートネットワークづくりに努めてまいります。
次世代の防災リーダーの養成につきましては、これまでにジュニア防災リーダーとして115人が認定されるとともに、市内中高生の42人が防災士資格を取得しております。
引き続き、新年度もジュニア防災リーダー養成講座を実施し、防災意識や行動力の高い生徒を育成してまいります。また、昨年発足した「本巣市ホープ防災リーダーズ」に東北研修を実施し、防災の大切さを五感で感じ、防災の中核となる意識と使命感を高めてまいります。さらに、新たな取組として、昨年、防災訓練の際や合併20周年記念イベントで、東北研修の成果や能登半島地震の被害状況、防災に関する豆知識など手作りで市民の方にわかりやすく啓発し、参加された市民からも大変好評のお声をいただきました。こうしたホープ防災リーダーズの活動を広く市民の方に知っていただくため、広報もとすなどに防災啓発の記事を掲載していき、市民の防災意識の向上につなげてまいります。
青少年国内派遣事業につきましては、日本で唯一地上戦となった地、沖縄を訪問し、歴史や地域づくりについて学び、発表することで、主体性と考える力を養い、学校や地域での未来のリーダーとして育成してまいります。
ウオーキング・ランニングのまちづくりにつきましては、市民の方が気軽に参加できるイベントとして内容を見直し、運動に取り組むきっかけづくりから運動習慣の意識づけにつなげ、市民の健康の保持・増進を図ってまいります。
歴史、文化の保存につきましては、昨年、市内で開催した「清流の国ぎふ文化祭2024」での盛り上がりをしっかりと継承し、これからも地域で大切にされてきた伝統文化が途絶えることがないよう、真桑人形浄瑠璃や能郷の能狂言、席田小の催馬楽(さいばら)「席田」、外山小の舞楽(ぶがく)「振鉾(えんぶ)」など、子どもたちが伝統文化に触れる機会を設けるとともに、伝統文化の良さを広く市内外に発信するなど、持続可能な歴史、文化活動の推進に努めてまいります。
まとめ
最後に、本巣市総合計画の策定について申し上げます。
本市のまちづくりの羅針盤であります「第2次本巣市総合計画」につきましては、平成28年度から令和7年度までの10年間を計画期間に、市が目指す将来像「自然と都市の調和の中で人がつながる活力あるまち・本巣」の実現を目指してさまざまな施策に取り組んできたところでございます。
しかしながら、昨今の社会情勢は想像を超えるスピードで変化し、市民ニーズも多様化しております。そのため、令和8年度からの新たな計画では、重点的に取り組むべき施策の明確化と、計画期間を4年間とすることでさまざまなニーズに対応していくことができる計画として策定に取り組んでまいります。
以上、市政運営に対する、私の所信の一端と令和7年度予算案などの概要につきまして、申し上げさせていただきました。
本巣市も合併して20年が経ち、その頃からまちの様相も大きく変わってまいりました。市役所新庁舎や都市公園「もとまるパーク」、東海環状自動車道や周辺道路網の整備、さらに企業の立地など、元気で笑顔あふれるまちづくりに向けた取組が着実に実を結びつつあると考えております。
しかし、もう一歩前へ、もう一歩先へと、この歩を止めることなく、東海環状自動車道の開通をチャンスととらえ、その効果を最大限に活かし、次の時代に向かっていけるよう、職員とともに知恵を出し、汗をかき、全力で取り組んでまいります。
市民の皆様から、「住み続けて良かった」、「本巣市に住んで良かった」と実感してもらえる、持続可能なまちへと発展し続けられるよう、厳しい財政状況での市政運営ではございますが、市民の皆様や企業の皆様にも協力を得ながら、取り組んでまいりたいと考えております。
結びに、議員の皆様をはじめ、市民の皆様の一層のご理解とご支援を心からお願い申し上げ、所信表明といたします。