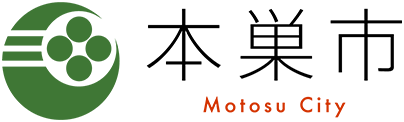埋蔵文化財
- [更新日:]
- ID:1126
埋蔵文化財について
埋蔵文化財とは、地下に埋もれたままになっている文化財のことで、1950年(昭和25年)の文化財保護法制定に伴い、新たに設けられた法的概念です。
埋蔵文化財には、土地と切り離すことのできない住居跡や古墳、貝塚などの遺構と、土器や石器などの遺物があり、これらが分布している地域を遺跡といいます。
埋蔵文化財が所在する場所は埋蔵文化財包蔵地といい、地下に埋もれているために範囲や内容が不明確で、これを明らかにするためには分布調査や、実際に地下を掘る試掘調査・発掘調査を実施することが必要です。こうして明らかになった包蔵地のことを周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等(※)を実施しようとする際には、文化財保護法第93条または第94条により届出・通知が義務付けられています。
※土木工事等…宅地開発、住宅建設、道路建設、河川工事、電源開発、その他の土を掘り返す全ての事業
※93条条文中にある「発掘」という文言は発掘調査だけをさすものではありません。地下・地上の遺跡に影響を与える掘削行為、盛土、抜根行為です。
土木工事等を行う前に
市内で土木工事等を行う場合、対象地が周知の埋蔵文化財であるか否かの確認が必要となりますので、工事の前に「埋蔵文化財包蔵地確認依頼書」を市教育委員会に提出していただき、確認後に事業者にご連絡します。
具体的に開発計画が決定される前から事前協議を行っていただければ、後の調整がスムーズに進行します。
社会教育課へFAXかメールで下記の依頼書と場所のわかる地図を送ってください。
(FAX番号058-323-2964、メールアドレスshakai-kyouiku@city.motosu.lg.jp)
様式ダウンロード
周知の埋蔵文化財包蔵地である場合
事業者と市教育委員会の調整
対象地が、周知の埋蔵文化財包蔵地であった場合、事業者と市教育委員会との間で手続き、試掘等の調整を行います。
対象地が農地の場合、本巣市農業委員会の指導により農業委員会への報告が必要です。
発掘の届出
埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合、事業者は工事着手の60日前までに「発掘の届出」を2部岐阜県知事宛で提出する必要があります(文化財保護法第93・94条)。また本巣市教育委員会教育長宛で1部「発掘調査承諾書」を提出する必要があります。
- 届出には土木工事等の内容を示す図面(住宅の配置図、基礎断面図等)を添付してください。
- 土地所有者以外に事業者、耕作者、占有者がみえる場合は、耕作者、占有者の発掘調査承諾書が必要です。
- 掘削を伴わない盛り土のみの造成であっても、今度住宅建設等を計画している場合には届出は必要です。
- 基礎などの計画が未定の場合、手書きの建物配置予定図や基礎伏せ図を添付いただくことでも構いません。
(試掘調査後計画が変更になった場合は、別途「工事計画変更の届出」を提出いただきます。) - 登記簿謄本、公図の添付は必要ありません。
- 住宅等の建て替えの場合、旧住宅の解体前に、解体にかかる図面と新築する建物の図面を添付した届出が必要です。
- 船来山古墳群、スボミ西古墳群などの古墳の場合、切土・抜根を伴う行為については影響を与える可能性がたいへん高いため、届け出が必要です。切土については何センチ以上等の取り決めはありません。群集墳であることと、船来山古墳群については特に今後追加指定を目指しています。近代以降の改変が行われていない場所での切土については慎重に対応するよう指導を受けています。
- 船来山古墳群国指定地内の工事については、文化庁長官の許可が無ければ工事は実施できません。現状変更届を提出いただいたのち、県の担当課へ相談し、慎重に対応させていただきます。
添付ファイル
 文化財保護法第93条に基づく届出様式 (ワード形式、29.50KB)
文化財保護法第93条に基づく届出様式 (ワード形式、29.50KB) 記入例 (PDF形式、95.51KB)
記入例 (PDF形式、95.51KB) 発掘調査承諾書 (ワード形式、15.09KB)
発掘調査承諾書 (ワード形式、15.09KB) 発掘調査承諾書(耕作者用) (ワード形式、25.64KB)
発掘調査承諾書(耕作者用) (ワード形式、25.64KB) 発掘調査承諾書(占有者用) (ワード形式、24.81KB)
発掘調査承諾書(占有者用) (ワード形式、24.81KB)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
現地確認調査
市教育委員会が試掘の上、範囲・性格等を確認します。この調査は、最初に事業者との調整の段階で行うことがあります。
- 試掘調査の費用は、国庫補助金と市費で行います。予算が足りない場合は予算調整の期間中調査実施を待っていただく場合があります。
- 市と契約している支援業務受注会社が重機とオペレーター、作業員を手配します。届出をいただいても日程の調整が困難な時期は、待っていただく場合があります。
- 本調査になる可能性もありますので、期間については十分にご考慮をお願いします。
県知事の指示
発掘の届出の後、県庁から事業者に指示があります。指示の内容は通常、下記の3つです。
- 工事着手前の発掘調査
- 工事中の立会い調査
- 慎重工事
※埋蔵文化財の重要度により、上記以外の指示がだされることもあります。
指示文書到着前の工事着工(造成、地盤調査等)は原則禁止されています。
埋蔵文化財発掘調査の届出
発掘調査主体は文化財保護法第92条により「埋蔵文化財発掘調査の届出」を、市教育委員会を通じて県に行います。
本発掘調査の実施
事業者と市教育委員会で、調査方法・日程・調査費用等について協議し、市教育委員会が主体となって本発掘調査を行います。
発掘調査にかかる費用については、事業者に協力を求めてその負担としています(文化財保護法第93条)。ただし、個人住宅建設等については公費負担となる場合があります。
発掘調査終了
市教育委員会から県へ調査終了の報告をします。
出土品は遺失物法(第13条)の適用を受け、発見者は警察署に「埋蔵文化財発見届」を、県に「埋蔵文化財保管証」を提出します。その後、県教育委員会による鑑査により文化財に認定されます。
周知の埋蔵文化財包蔵地でない場合
埋蔵文化財包蔵地以外の土地での土木工事等にあたっても、工事中の遺跡の不時発見を避けるため、事前の試掘調査あるいは土層確認のための立会いに協力をお願いする場合があります。
発掘調査以外で埋蔵文化財を発見した場合
発掘調査以外で、例えば土木工事中に、遺物・遺跡などの埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更せず、すみやかに県に「遺跡発見の届出」をする必要があります(文化財保護法第96・97条)。
県は、その遺跡が重要なものであり、保護のための調査を行う必要があると認めるときは、その現状を変更するような行為の停止または禁止を命ずることができます。その期間は3か月ですが、調査の進行にあわせて6か月まで延長できます。
また、県は届出がされなかった場合でも、現状変更停止等の措置を執ることができます。
県の指示のもと、市教育委員会が主体となって調査等を行います。
埋蔵文化財に関する手続きの流れ
下記のPDFファイルに、埋蔵文化財に関する手続きの流れがまとめられています。
添付ファイル

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。